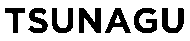Autism at Work 12年:16か国240人、請求処理「数日→20分」の裏側
独SAPのニューロダイバーシティ(ND)採用プログラム「Autism at Work」は、2013年の開始から12年。公式サイトは16か国・240人超、外部発表では定着率90%を掲げる。口頭面接を“仕事そのもの”で置き換える仕組みは、請求処理の数日→20分短縮という象徴的な成果を生み、ITとバックオフィスの品質を押し上げた。法定雇用率の引上げと合理的配慮義務化が進む日本にとって、同社の設計は「順守と生産性の両立」を示す実証だ。

SAPが行ったのは、採用の入口を“話す力”から“作る力”へと切り替えることだった。候補者は数日間、実務に近い課題(ワークサンプル)に取り組む。たとえば、テスト観点表の作成、ログからの異常抽出、簡易的な自動化スクリプト、請求処理の手順設計などだ。成果物は、その場の機転よりも再現性と正確さを映し出す。入社後はSOP(標準作業手順)とチェックリストで立ち上がりを導き、**ピアメンター(同僚指導役)**が週次でフォローする。評価・配慮・育成があらかじめ“つながっている”点が、プログラムの核だ。
象徴事例:請求処理「数日→20分」
アルゼンチン拠点で、ある社員が複雑な社内横断の請求処理を自動化した。導入前は2~3日かかった処理が、ツール導入後は20分に短縮されたという。単なる美談ではない。要件の分解、例外処理の定義、レビューの型――手順の言語化が自動化を可能にした。ND人材の強みであるパターン認識や規則への粘り強さが、ここで威力を発揮する。
職域の広がり:ITとバックオフィスの“地味な要”を強くする
Autism at Workの配属先は、QA(品質保証)、テスト自動化、データ前処理、運用監視、ドキュメント整備、さらには経理の仕訳・照合まで多岐にわたる。共通項は、手順が定義でき、結果が測定できることだ。SAPは公式ページで、取り組みが世界16か国に広がり、240人超の同僚が活躍していると掲げる。地域ニュースでは**215人/15か国・定着率90%**の数値も示され、離職の少なさが継続的な生産性向上の背景になっている。
日本への示唆:順守から“業務改善”へ
日本では2024年4月に民間の法定雇用率が2.5%に引き上げられ、2026年7月に2.7%となる見込み。合わせて合理的配慮の提供は事業者の法的義務になった。SAPの設計は、これらをコストではなく改善の起点として捉える視点を提供する。すなわち、
採用段階でワークサンプルにより“できる仕事”を可視化する。
入社後はSOP/チェックリストとピアメンターでMTTR(平均復旧時間)や欠陥密度といったKPIに直結させる。
定着率の高さを再教育コストの抑制と暗黙知の蓄積に変換する。
現場実装:3つの要点
① 評価を職務起点へ――求人票の「コミュ力」や「柔軟性」を、成果物に翻訳する。例:テスト計画書の雛形と観点表を事前配布し、候補者に具体的な改善提案を書き込んでもらう。
② 配慮は“個別対応”でなく“運用ルール”に――照明・ノイズ・休憩の取り方、指示のテキスト化、打合せのアジェンダ事前配布を全員向けルールにする。結果的にチーム全体の誤解・手戻りを減らせる。
③ KPIで投資対効果を可視化――欠陥検出率、一次解決率、KEDB(既知エラーDB)更新件数、自動化率を四半期レビュー。Before/Afterの改善が見えれば、雇用はプロジェクトから計画ヘッドカウントに昇格する。
ケース:中堅メーカー(日本)の導入1年
基幹システム刷新に伴い、回帰テストがボトルネック化。従来の面接では採用が難航したが、ワークサンプルに切り替え、テスト観点の抽出と境界値テストの設計を課題化。入社後はSOPとペアレビューを運用し、MTTRは平均27%短縮、エスケープバグ率は34%減。KEDBの更新が習慣化し、障害対応の再現性が上がった。管理職は**SBI(状況・行動・影響)**でフィードバックを記録し、主観のブレを抑制した。
用語解説(専門家以外の方向け)
ND(ニューロダイバーシティ):自閉スペクトラム、ADHD、学習障害、ディスレクシア等を含む脳や認知の多様性のこと。病気の有無で線引きせず、認知特性の違いを人材戦略に活かす考え方。
ワークサンプル:口頭面接の代わりに、実際の業務に近い課題で能力を測る方法。**“仕事で測る”**と覚えると分かりやすい。
SOP(標準作業手順):手順や注意点を文書化したもの。誰がやっても同じ結果が出ることを狙う。
KEDB(既知エラーDB):過去の障害と対処法のナレッジ集。更新が進むほど復旧が速くなる。
MTTR(平均復旧時間):障害発生から復旧までの平均時間。短いほど運用が安定している。
QA(品質保証):不具合を早期に見つけ、品質を保つ活動全般。
定着率:一定期間で働き続けている人の割合。高いほど採用・教育コストが有効活用される。

展望
クラウドやAIの普及で、定義可能で測定可能な業務は増え続ける。SAPの事例は、障害者雇用をコストではなく品質向上のエンジンへと変換する現実解だ。面接室の会話を少し減らし、成果物と手順を少し増やす――それだけで、現場の空気は変わる。
TSUNAGU MEDIA 編集部
障害者雇用でお悩みの方、障害者(ニューロダイバイシティ)社員の職域拡大に向けたリスキリングをご検討されている方は、採用から育成まで一貫した支援が可能なTSUNAGUに、お気軽にご相談ください。
© 2026 TSUNAGU.LLC