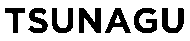米マイクロソフトが進めるニューロダイバーシティ(ND)採用が10年を迎え、選考を「雑談中心の面接」から「数日間のワークサンプル(実務課題)+コーチング」に置き換える独自モデルは、2024年にはデータセンター職へも拡張された。日本では2024年4月に民間の法定雇用率が2.5%へ引き上げられ、2026年7月に2.7%となる予定。合理的配慮の提供も事業者の義務化が進む中、同社の実践は“コンプライアンス対応”を超えてIT部門の生産性向上を狙う企業に示唆を与える。

米ワシントン州レドモンド発。マイクロソフトは2015年ごろから、発達障害や学習障害、注意特性など幅広いND人材を対象に、選考の「入口」を再設計してきた。公式発表によれば、候補者は数日にわたり実務に近い課題を行い、コーチとともに自身の働き方を確認する。従来の一回限りの口頭面接よりも、実務で評価する公平性を高める狙いだ。さらに同社はマネジャー向けのコーチング研修を制度化し、合否判定だけでなく入社後の立ち上がりを見据えた支援へと発想を移した。
こうした取り組みは2024年、データセンター領域に広がった。米国内の複数拠点で、データセンター・テクニシャンやクリティカル・エンバイロンメント・テクニシャンといった職種にND人材の応募経路を開いた。物理設備を扱う現場では、手順の標準化やチェックリスト運用、光・音などの感覚刺激への配慮が生産性と安全性を左右する。ND人材のパターン認識や反復タスクへの強さは、この環境と相性が良い――同社のブログはそう示唆する。
選考モデルの要は三つある。第一に、成果物で測ること。ホワイトボードの雑談や即答の巧拙ではなく、ログからの異常抽出、テストケース設計、運用手順の文書化など、実際の仕事と連動したアウトプットで評価する。第二に、働き方の事前共有。候補者は自分に合うコミュニケーション手段や環境調整(照明、ノイズ、休憩の取り方)を、選考過程で明らかにできる。第三に、現場側の準備。マネジャーとチームが期待値・優先順位・完了定義(DoD)を言語化し、オンボーディングを構造化しておく。これらは「特別扱い」ではなく、品質管理としての業務標準化に等しい。
この設計が効果を上げる背景には、IT業務の再現可能性がある。品質保証(QA)やソフトウェアテスト、ログ解析、データ前処理、運用監視などは、手順の視覚化とレビューの型が定まれば、欠陥検出率やMTTR(平均復旧時間)といったKPIに反映されやすい。社内外の事例では、ND人材を含むチームがバグ検出や処理速度で優位を示すケースが複数報告されている。マイクロソフトのプログラムは、採用手法の変革がマネジメントの質を底上げすることを立証した格好だ。
一方、日本企業の現場では、障害者雇用が“人手不足の穴埋め”または“法対応”として切り離されがちだ。2024年4月に民間の法定雇用率が2.5%に引き上げられ、2026年7月には2.7%となる。さらに合理的配慮の提供が事業者の義務となったことで、採用から就労、評価までのプロセス設計の見直しは待ったなしである。問いは単純だ――「どの職務で、どんな成果を出す人を、どう評価し、どう支援するか」。この問いに、レドモンドのモデルは具体的な答えを持っている。
実装の第一歩はジョブ分析だ。たとえばQAなら、「回帰テストスイートの更新件数」「エスケープバグ率の低下」「テストカバレッジの維持/向上」といった成果指標を先に置く。次に、選考で扱うワークサンプル(テスト観点表の作成、境界値テストの設計、ログからの異常パターン抽出)を用意する。面談は、口頭の機転を見る場ではなく「成果物のレビュー」であるべきだ。入社後はチェックリストとSOP(標準作業手順)を配布し、ピアメンター制度で週1回のフォローを担保する。環境配慮(ノイズ対策、照明、休憩、リモートと出社の最適化)は、個別対応に留めずチームの運用ルールとして文書化する。
第二歩はマネジャー育成。期待値と優先順位、締切、レビュー観点をテキストで明記し、**SBI(状況・行動・影響)**などフィードバックの型を共通言語にする。障害特性の理解は重要だが、目的は“特性に詳しくなること”ではない。仕事のやり方を合意形成できる管理職を増やすことである。マイクロソフトが示すように、マネジャー支援はプログラムの中核だ。
第三歩はKPIの可視化。Before/Afterで欠陥密度や初動時間、KEDB(既知エラーDB)更新件数、自動化率を四半期ごとにレビューする。数字の改善が確認できれば、採用は単発ではなく計画的なヘッドカウントに移行できる。ここで助成金の活用を併走させれば、立ち上げ費用の一部をオフセットできる。計画の明瞭さは、現場の納得感と定着に直結する。
本紙の取材に応じた国内の人事責任者は、「面接を準備する時間をワークサンプルの設計に置き換えた。結果として、入社前から合理的配慮の内容が擦り合わさり、立ち上がりが早くなった」と語る。重要なのは、“善意”のプログラムではなく業務設計としての一貫性である。採用ページに「ND採用」を掲げるだけでは何も起きない。職務定義、評価、オンボーディング、管理職育成、KPI評価までを一本の線で結ぶこと――それがレドモンドの10年が教える核心だ。

展望
クラウドとAIに支えられた運用現場は、今後さらに定型化と自動化が進む。異常検知、データクレンジング、テスト自動化、ドキュメント整備――“静かな集中”が価値を生む仕事は減らない。障害者雇用は、法令順守のチェックボックスではない。ITの品質と速度を上げるための人材戦略である。
TSUNAGU MEDIA 編集部
障害者雇用でお悩みの方、障害者(ニューロダイバイシティ)社員の職域拡大に向けたリスキリングをご検討されている方は、採用から育成まで一貫した支援が可能なTSUNAGUに、お気軽にご相談ください。
© 2026 TSUNAGU.LLC