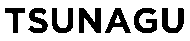米JPMorgan Chaseの「Autism at Work」は2015年に米デラウェアで小さく始まり、現在は9か国・40職種超へ広がる。外部報道では、導入半年で48%速く、最大92%高生産という成果が示された。口頭中心の面接をワークサンプル(実務課題)に置き換え、QA(品質保証)やソフトウェアテスト、運用の“粒度”をそろえたことが鍵だ。法定雇用率引上げと合理的配慮義務化が進む日本でも、業務設計から入るND(Neuro Diversity)採用は、品質とスピードを同時に押し上げる現実解となる。

マンハッタンの会議室で語られたのは“善意の雇用”ではなかった。採用の入口を、雑談型の面接から実務そのものへ――。パイロットでは、候補者にログからの異常抽出やテストケース設計などの課題を提示し、成果物で評価。入社後はマネジャー研修と現場のチェックリスト、レビューの型で立ち上がりを支える。この再設計が、半年で48%のスピード向上、役割によっては最大92%の高生産という数字につながったと、複数の外部記事が報じている。
仕組み――“話す力”より“つくる力”を測る
同社の選考は、数日間のワークサンプルを主軸とし、候補者が必要とする合理的配慮(照明・ノイズ・休憩・指示のテキスト化など)を事前にすり合わせる。評価の論点は、再現性と正確さ、そして手順の言語化。面接時間の多くを成果物レビューに割くことで、“入社後に求める働き方”と“当人の強み”が初日から一致する。
どこで成果が出るか――QA/テスト/運用が起点
最初に目に見える数字が動くのはQA(品質保証)とソフトウェアテストだ。受入基準と完了定義(DoD)を明確にしたチケット運用にすると、欠陥検出率とエスケープバグ率が改善する。運用監視では、一次切り分けとアラート閾値の共通言語化により、MTTR(平均復旧時間)が短くなる。ND人材のパターン認識と反復耐性は、こうした“定義できて測れる仕事”で力を発揮する。
現場の声――「面接準備」を「課題設計」に置換
採用担当が語る。「これまで面接で使っていた時間を、課題(ワークサンプル)設計にあてた。入社前から配慮の内容が具体化し、立ち上がりが速くなった」。現場のマネジャーは、SBI(状況・行動・影響)でフィードバックを記録。主観のブレを抑え、チーム内の心理的安全性も高まったという。
日本企業への示唆――“順守”から“業務改善”へ
日本では2024年4月に民間の法定雇用率が2.5%へ引上げ、2026年7月に2.7%となる予定。合理的配慮の提供も事業者の義務だ。JPMorganの設計は、これらをコストではなく改善の起点に変える。
募集・選考:求人票の抽象語(例:コミュ力)を成果物に翻訳。テスト計画書の雛形を配布し、候補者に観点の追記や改善提案を書いてもらう。
オンボーディング:SOP(標準作業手順)とチェックリスト、ピアメンターで週次フォロー。照明・ノイズ・休憩などの配慮は“個別対応”に留めずチームの運用ルールへ。
KPI運用:四半期ごとに欠陥密度/一次解決率/KEDB(既知エラーDB)更新件数/自動化率をBefore/Afterで評価。改善が見えれば、雇用は単発から計画ヘッドカウントへ移行する。
事例(編集部試算)――中堅SaaS企業の90日プラン
・Day1–14:
職務分析。QA/運用の成果指標(欠陥検出率、MTTR、アラート誤検知率)を定義し、ワークサンプルを準備。
・Day15–45:
2日間の体験選考を実施。成果物レビューで合否と配慮を同時に決める。
・Day46–90:
ピアメンターを中心にSOP運用を定着。KEDB更新数と初動時間をダッシュボードで可視化。
最初の四半期で、MTTR 20~30%短縮、エスケープバグ率 20%改善を目標に置く。
※用語解説(専門家以外の方向け)
ワークサンプル:面接の代わりに実務に近い課題で能力を測る手法。「仕事で測る」と覚えるとわかりやすい。
QA(品質保証):不具合を早期に見つけ、品質を保つ一連の活動。テスト設計やレビュー、計測を含む。
DoD(完了定義):そのタスクが完了とみなせる条件。曖昧さを減らし、手戻りを防ぐ。
MTTR(平均復旧時間):障害発生から復旧までの平均時間。短いほど安定運用。
KEDB(既知エラーDB):過去の障害と対処法を蓄えたナレッジ庫。更新が進むほど復旧が速い。

展望
生成AIの普及で、テストの自動化やログ解析など“定義できるIT業務”はさらに増える。ND人材の強みと組織の標準化が噛み合えば、品質・速度・定着の三拍子が揃う。JPMorganの示した数字は、設計が行動を変え、行動がKPIを動かすことの裏返しにほかならない。
TSUNAGU MEDIA 編集部
障害者雇用でお悩みの方、障害者(ニューロダイバイシティ)社員の職域拡大に向けたリスキリングをご検討されている方は、採用から育成まで一貫した支援が可能なTSUNAGUに、お気軽にご相談ください。
© 2026 TSUNAGU.LLC