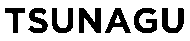初めての障害者雇用で迷わない!中小企業が最初に知るべき実務ガイド
障害者雇用が「初めて」の中小企業では、「どこから手をつければいいのかわからない」と悩む担当者が多いものです。本記事では、法定雇用率の基礎知識から、配属部署や業務の切り出し、支援制度や相談窓口まで、具体的かつ段階的に進め方を解説します。
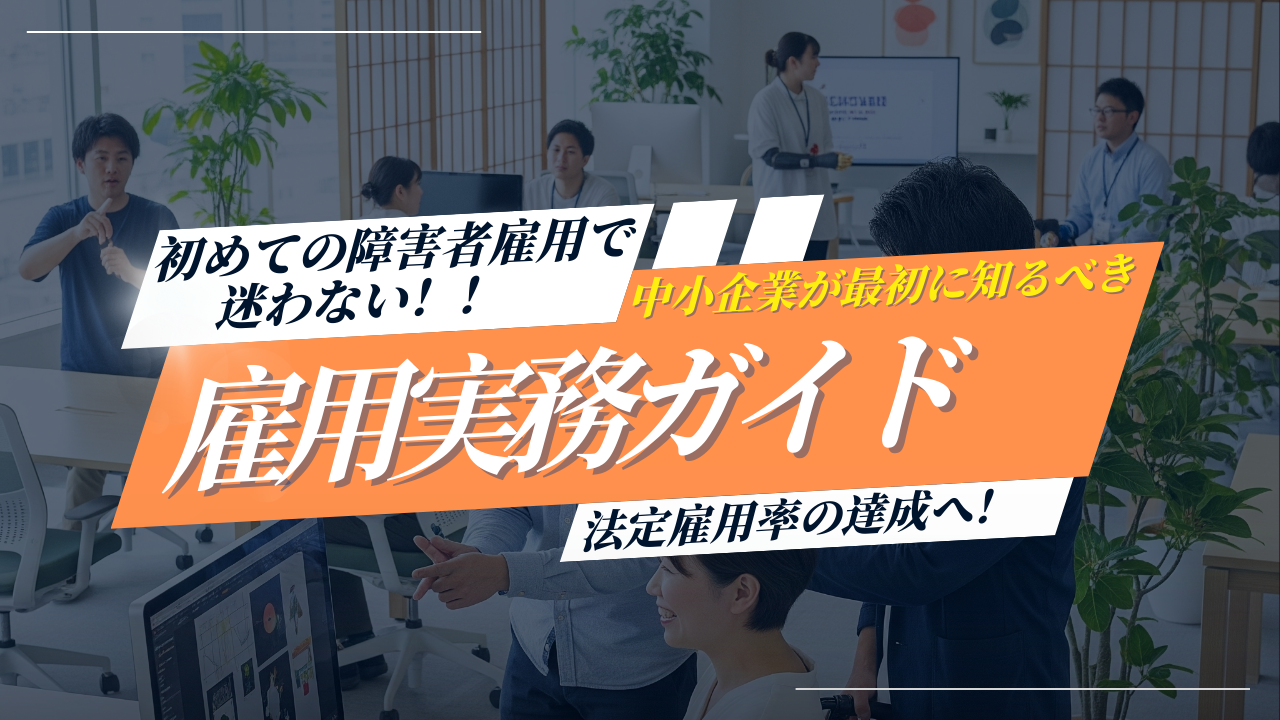
1. まずは「なぜ障害者雇用が求められるのか」を理解しよう
法定雇用率の義務
従業員が40人以上の企業では、2.5%(2026年7月から2.7%)の障害者雇用が義務化されています。
つまり、40人であれば1人以上、400人なら10人以上を雇う必要があります。義務を果たさないリスク
雇用が不足すると納付金が発生したり、企業名が公表される可能性があります。
一方で、達成企業は半数に留まっており、多くの中小企業がまだ対応に悩んでいます。
2. 進め方は「業務選び→採用→定着支援」の6ステップ
中小企業で初挑戦の担当者でも進めやすいよう、業務の切り出しから長期定着までを6ステップで説明します。
ステップ1:配属部署と切り出せそうな業務を選ぶ
まず部署を決める
各部署の責任者と対話し、「障害の特性に応じた業務がどこにあるか」を探りましょう(例:座ってできる作業がある部署や、定型業務が多い部署など)。業務を洗い出す
電話対応、備品管理、書類整理など、部署の業務を全部リストしてみることで、担当可能な業務が見えてきます。タスクまで細かく分解する
例:書類整理→(1) 日付順に並べる → (2) ファイリング → (3) 棚へ戻す、など。このように明確化すると、適性に応じた業務アサインが容易になります。
ステップ2:採用の計画を立て、募集を開始する
どんな人材が必要か明確に
上のタスクから求める特性(正確さ、視覚的理解力など)を洗い出し、人物像を描きます。募集方法を選ぶ
ハローワーク経由で無料募集し、職場定着の支援も併用。
就労移行支援事業所や特別支援学校を通じて紹介してもらう方法も◎。
ステップ3:採用面接と受け入れ態勢の整備
面接時の配慮
障害者の特性を理解し、無理のない内容で進めることが重要です。環境とサポート体制を整える
職場環境のバリアフリー化や、社内サポーター制度の導入などで安心できる環境を整えましょう。
ステップ4:採用後の定着・フォロー体制を構築
定着支援がカギ
ジョブコーチ制度や職場内サポーター制度など、外部機関と連携しながら支援体制を作ることが大切です。合理的配慮の導入
マニュアル化や視覚的支援、ITツール活用などで、障害特性に応じた業務遂行を支援します。
ステップ5:定期的に見直し、業務や配置を調整する
業務量や難易度などを定期的に点検
実際の作業を見ながら、「もう少しできそう」「逆に負担があるかも」という柔軟な対応を行う習慣をつけましょう。
ステップ6:長期雇用に向けた体制づくり
再チャレンジやスキルアップの機会も準備
成長意欲のある方には、新たな業務チャレンジの場を提供し、定着を促進しましょう。
3. 障害者雇用を支える相談窓口・助成制度
障害者雇用ナビゲートなど、支援体制あり
雇用前の環境整備から雇用後の支援まで一貫して対応してくれるサービスも活用しましょう。助成金で費用を軽減する工夫も
例:有期→無期や正規転換で最大120万円の「キャリアアップ助成金」。
また、障害者向けの職場訓練施設の設置に対しては「人材開発支援助成金」が活用可能です。
4. ケーススタディ:TSUNAGUの人材育成型障害者雇用支援
当社TSUNAGUでは、単なる「雇用率達成」ではなく、障害者社員がスキルを身につけ、自立的に働ける人材育成型雇用を支援しています。
スキル習得型研修の提供
障害者社員が安心して学べる研修プログラムを提供し、PCスキルやビジネスマナー、業務に必要な基礎力を習得できるよう支援しています。業務切り出しのコンサルティング
企業ごとに業務フローを分析し、障害者社員に適した業務を選定・再設計。実際の運用まで伴走支援します。職域拡大とリスキリング支援
単純作業にとどまらず、徐々に業務の幅を広げるリスキリングを行い、キャリア形成につなげています。定着フォローと企業内研修
企業の管理者・従業員に向けた障害理解研修を行い、共生できる職場文化を醸成。定着率向上に直結しています。
5. まとめ:初めての担当者でもここから始めよう
| 項目 | 実務アクション |
|---|---|
| 法令理解 | 法定雇用率や罰則リスクを押さえよう |
| 業務設計 | 配属部署の業務を洗い出し、タスク化 |
| 採用方法 | ハローワークや支援機関を活用 |
| 受け入れ体制 | 環境改善 × 定着支援を整備 |
| 支援活用 | ジョブコーチ、助成金、相談窓口を活かす |
| 人材育成 | TSUNAGUの研修・リスキリング支援を導入 |
障害者雇用初挑戦の企業担当者さまへ:
まずは「できること」から一歩ずつ始めてみましょう。制度と支援機関をしっかり理解し、業務を丁寧に設計することが成功の近道です。TSUNAGUの人材育成型障害者雇用支援を活用すれば、採用から育成・定着まで一貫して伴走できます。ぜひお気軽にご相談ください。