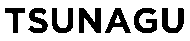「障害者雇用を進めたいが、現場から理解が得られない」「負担やストレスが増えるのではないか」という声は多くの採用担当者が直面する課題です。本記事では、現場の理解を得ながら無理なく障害者雇用を進める方法として、在宅勤務を活用したTSUNAGUの人材育成型雇用支援サービスを解説します。
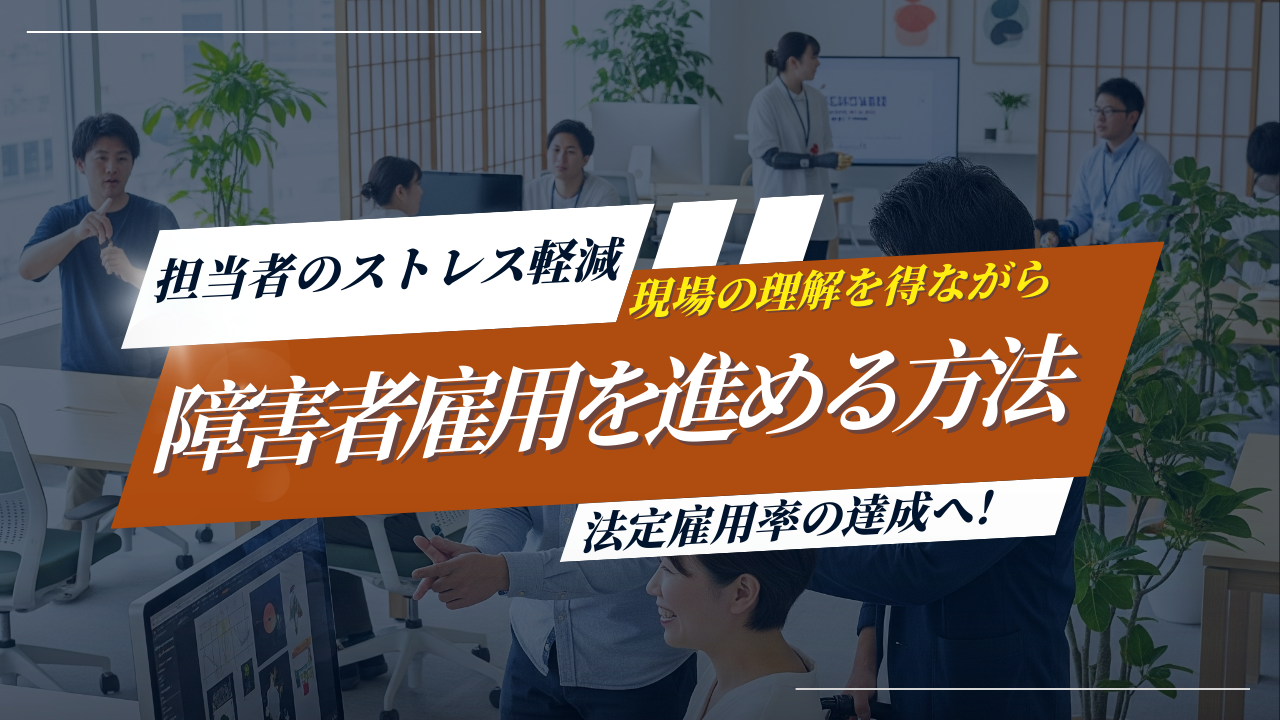
1. 採用担当者が直面する“あるある”の課題
障害者雇用を進める際、採用担当者は次のような苦労をよく経験します。
「現場から反発される」
「余計な仕事が増える」「サポートの余裕がない」と現場社員から声が上がる。「障害特性が理解されない」
精神障害や発達障害など見えにくい障害に対し、誤解や不安が広がる。「せっかく採用しても定着しない」
サポート体制が整わず、短期間で退職してしまう。「調整役として疲弊する」
現場と経営層の板挟みになり、採用担当者が一番のストレスを抱えるケースも多い。
これらはどの企業でも起こり得る“あるある”です。しかし、解決策はあります。
2. なぜ現場の理解が得られないのか
障害者雇用に対して現場が抵抗を示す背景には、次の要因があります。
業務負担の増加への懸念:教育やフォローに時間を取られるのではないか。
障害特性への理解不足:どう対応してよいかわからず、不安が大きい。
過去の失敗体験:定着しなかった経験から「また同じことに」と思われてしまう。
こうした課題を無視して雇用を進めると、現場のストレスが増し逆効果になってしまいます。

3. 在宅勤務から始めるという選択肢
現場の理解を得ながら障害者雇用を進めるには、在宅勤務から小さく始めるのが有効です。
(1)現場の負担を抑えられる
在宅勤務であれば直接的なサポートや物理的な環境整備が不要。現場社員への負担を最小限にできます。
(2)任せる業務を少しずつ拡大できる
まずはデータ入力や資料整理など定型業務から始め、実績を積んでから徐々に幅を広げる。成果が見えることで自然に現場の理解が進みます。
(3)法定雇用率の達成にも有効
在宅勤務の障害者社員も雇用率にカウントされるため、現場の負担を増やさず法定雇用率を満たすことが可能です。
4. TSUNAGUの人材育成型雇用支援サービス
TSUNAGUでは、現場の理解を得ながら雇用を進めるための人材育成型支援を提供しています。
在宅業務設計コンサルティング
業務フローを分析し、在宅で任せやすいタスクを抽出。切り出しから実運用まで伴走します。スキル習得型研修
在宅で働く障害者社員がPCスキルや業務遂行力を高められる研修を提供。段階的な職域拡大
短時間・単純作業から始め、習熟度に応じて業務をステップアップ。中長期的な戦力化を実現します。定着支援と理解促進
障害理解研修やフォロー面談を実施。現場社員の不安を解消しながら、社内の共生文化を育てます。
5. 導入ステップ
- ヒアリング:現場の課題やストレスを把握。
業務の棚卸し:在宅勤務で切り出せる業務を明確化。
人材紹介と研修:スキルに合わせた人材を紹介し、必要な研修を実施。
小さく開始:少量の業務からスタートし成果を共有。
実績を基に理解を拡大:成功体験を現場に浸透させ、理解を広げていく。
6. まとめ:現場と歩調を合わせた雇用が成功の近道
障害者雇用を進める上で、現場の理解は欠かせません。無理に受け入れを迫るのではなく、在宅勤務から始めて少しずつ業務を任せ、実績を積み重ねることで自然に理解が深まります。結果として、法定雇用率を達成しながら現場のストレスも抑えることができます。
TSUNAGUの人材育成型雇用支援サービスなら、採用担当者の悩みに寄り添い、現場のストレスを最小限に抑えながら雇用を進めることが可能です。ぜひお気軽にご相談ください。
© 2026 TSUNAGU.LLC